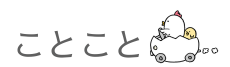急ぎの書類を送る際は、速達郵便の利用が便利です。
通常、速達郵便で送る場合、封筒の右上に赤いマーカーで線を引くことが一般的な手順とされています。
しかし、困ったことに赤いマーカーが見当たらない時もありますよね?
「確か前にはあったはず」と家を探しても、見つかるのは細い赤いボールペンだけ。
実は、この赤いボールペンを使用しても速達郵便を利用することができます。
この記事では、ボールペンを使った速達郵便の手書きマーキング方法についてご説明します。
ボールペンを使った速達マーキングの手順
速達の印つけは、赤いボールペンでも問題ありません。
基本的なマーキング方法
速達郵便を出す際の基本的なマーキング方法についてお話しします。
日本郵便の公式ガイドラインでは、速達を使用する際には封筒や郵便物の「表面の右上部」に赤い線を引く必要があります。
郵便物が横長の場合は、その右側部にマーキングすることになります。
従って、速達郵便を使う場合は、右上に赤い線を引くことが必須です。
私自身、以前はこのマーキングの正しい方法をそれほど詳しく知らず、「速達」とだけ赤いマーカーで記入して囲んでいました。
しかし、封筒の右上に赤い線を引くことで正式に「速達」と認識されるのです。
赤いボールペンだけでも速達郵便は大丈夫!
「手元に赤いボールペンしかないけど、これで速達は可能?」と不安に思う方もいるでしょう。
しかし、ご安心ください。
赤いボールペンがあれば、速達郵便として問題なく扱えます。
日本郵便の公式指示では、「赤い線を引いてください」とありますが、その線の太さや長さについて具体的な制限は設けられていません。
そのため、赤いボールペンで郵便物の右上部(横長の郵便物の場合は右側部)に線を引くだけで、速達として認識されるのです。
さらに、「速達」という文字を線に加えることで、郵便の性質をよりはっきりとアピールすることができます。
これだけでは不安に感じることもあるかもしれません。
特に重要な内容を含む郵便を送る際には、細いボールペンでのシンプルなマークだけでは郵便局員の目に留まらない可能性も考えられます。
そこで、郵便物のより目立つ部分、たとえば表面の左下に「速達」と大きく書き足し、文字を四角で囲むことを推奨します。
これにより、送る意志を明確にし、郵便局員が見落とすことなく確実に速達で処理されるよう助けられます。
速達封筒の裏面への記入方法
速達封筒の裏面には、通常の郵便物と同様に差出人情報を記入します。
具体的には、「郵便番号」「住所」「氏名」を封筒の裏面左側に記述してください。
速達封筒の裏面に「速達」と書く必要はありません。
速達郵便の料金に関して
速達郵便の料金は、標準的な郵便料金に加えて「速達料金」が加算されます。
例として、25g以内の通常郵便で84円の場合、追加の速達料金260円が必要で、合計では344円となります。
重量に応じて、250gまで260円、1kgまで350円、4kgまで600円と速達料金が設定されています。
※2024年の秋頃に郵便料金の値上げが予定されています
郵便局での速達郵便の手続き方法
速達郵便を利用する際には、郵便局へ直接行く方法が最も確実です。
郵便局の窓口で「速達で送りたい」と伝えれば、窓口のスタッフが必要なマーキングや料金計算を含めた全ての手続きを行います。
これにより、自宅での誤計算を防ぐことができます。
ただし、郵便局が閉まっている日曜日などは自分で切手を貼ってポストに投函する必要があります。
このとき、料金が不足している場合は郵便が差出人に戻されることがありますので、料金の計算には十分注意しましょう。
また、差出人の住所が不明瞭な場合は、受取人が追加料金を支払うことになることもありますので、その点も留意が必要です。
まとめ
本記事では、「赤いボールペンだけで速達郵便を送ることはできるのか?」という問いに答えています。
速達郵便は日常的に使うものではないため、使用する際に「この方法でちゃんと届くのだろうか?」という不安を抱く方も少なくありません。
私も過去には、封筒の右上に特別な線を引かずに、単に「速達」と赤いペンで記入して郵便物を送っていましたが、その方法でも問題なく配達されていました。
重要なのは、「速達で送る」という明確な意志表示と、正しい料金の支払いがされていることです。
これらが確保されていれば、郵便物は確実に届けられます。
それでも、もっとも安全で確実な方法は、郵便局に直接郵便物を持ち込むことです。
可能であれば、郵便局の窓口で手続きをしてもらうことをお勧めします。